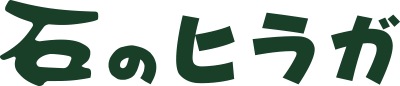冬至
投稿日:2023/12/22
12月22日は冬至です。
冬至は、1年の中でいちばん昼の時間が短く、夜の時間がいちばん長い日です。
冬至には様々な習慣や行事があり、それには特定の食べ物や行事が関連していることがあります。
例えば、中国の冬至には「冬至団子」と呼ばれる特別な団子を食べる習慣があります。
各地域や文化で異なる冬至の習慣が存在します。
日本では
冬至の食べ物は「ん」がつくもので運盛りかぼちゃは別名「南瓜(なんきん)」で「ん」がつく
冬至の日の食べ物には、よく知られるかぼちゃの他、「冬至粥」や、
地方によって小豆とかぼちゃを煮た「いとこ煮」を食べるところなどもあります。
冬至の食べ物…かぼちゃ/南瓜(なんきん)
冬至の食べ物であるかぼちゃは別名「南瓜(なんきん)」だから、「ん」のつく運盛り!
冬至には「ん」のつくものを食べると「運」が呼びこめるといわれています。にんじん、だいこん、れんこん、うどん、ぎんなん、きんかん……など「ん」のつくものを運盛り といい、縁起をかついでいたのです。運盛りは縁起かつぎだけでなく、栄養をつけて寒い冬を乗りきるための知恵でもあり、土用の丑の日に「う」のつくものを食べて夏を乗りきるのに似ています。
「冬至の七種(ななくさ)」で運も倍増!
運盛りの食べものに「ん」が2つつけば「運」も倍増すると考え、
それら7種を「冬至の七種(ななくさ)」と呼ぶことがあります。