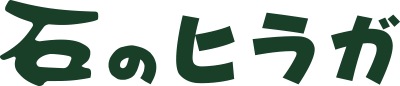新嘗祭
投稿日:2023/11/21
「新嘗祭」(しんじょうさい)は、古代日本の神道祭りで、新しい穀物の収穫を感謝し、神への祭儀を行う伝統的な祭りです。この祭りは、古代から続くもので、新しい穀物が日本の神道における祭りの一つであり、地域によって異なる形で祝われています。 新嘗祭の主な特徴と舞台には次のような要素が含まれます: 1 . 新しい収穫物の感謝:祭りの中心は、新しい穀物、特に新しいお米への感謝があります。新しい穀物は神聖視され、それを神に捧げることが行われます。
毎年11月23日、全国の神社において新嘗祭が行われます。「新」は新穀(初穂)、「嘗」は御馳走を意味し、天照大御神(あまてらすおおみかみ)はじめすべての神様に新穀をお供えして、神様の恵みによって新穀を得たことを感謝するお祭りです。
五穀豊穣を祈願した2月17日の祈年祭と相対するお祭りで、この日、宮中では天皇陛下が感謝をこめて新穀を奉るとともに、御自らも召し上がります。
新嘗祭の起源は古く、「古事記」にも天照大御神が新嘗祭を行ったことが記されています。今は新嘗祭から勤労感謝の日へと呼び名は変わっていますが、「収穫を祝い感謝する」という本来の意味は変わってはいません。
一方、新嘗祭のうち新天皇が即位して最初のものを大嘗祭(だいじょうさい)といいます。大嘗祭は、即位の時期が7月までならばその年に、8月以降では翌年に行われます。5月に御世替りを迎えた2019年は、11月14、15日に大嘗祭の中心的となる「大嘗宮の儀」が行われました。
大嘗祭で使われるおコメは、カメの甲を使った「亀占」によって産地が決められます。それを「斎田点定の儀」といい、2019年の大嘗祭に向けては、5月13日に皇居・宮中三殿で古式ゆかしく行われました。東日本(悠紀(ゆき)地方)から栃木県、西日本(主基(すき)地方から京都府が選ばれ、今後、宮内庁と各県の関係者で具体的な場所を決定し、秋の「斎田抜穂の儀」で新穀を収穫、お供えられます。