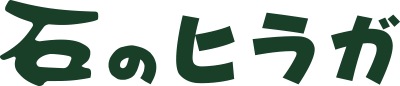2月3日は節分
投稿日:2024/01/30
節分に食べる巻き寿司は「恵方巻き」と呼ばれ、その年の縁起の良い方角(恵方)を向いて食べるとされています。恵方巻きは、七福神にあやかって7種類の具材を巻いた太巻き寿司で、巻き寿司を鬼の金棒に見立て、それを退治する意味もあるといわれています。
恵方巻きは、立春の前日である節分の日(2月3日)に食べるのが通例です。恵方巻きを食べる理由は、陰陽道でその年の福徳を司る年神様がおる方向、恵方に向かって事を行なえば、「何ごとも吉」とされたことに由来しています。また、恵方巻きにはさまざまな具材(=福)が巻き込まれており、食べる途中でしゃべるとせっかくの福が逃げてしまうと言われています。
恵方巻きには、かんぴょうや伊達巻など、特別な意味を持つ具材が含まれます。かんぴょうは「長生きできるように」、伊達巻は「金運」を意味します。
恵方巻きは、地域やお店によって「恵方寿司」「丸かぶり寿司」「招福巻き」「開運巻き」など、さまざまな呼び名があります
節分の由来は古い時代にさかのぼります。節分は主に陰陽道や民間信仰に関連するもので、季節の変化や邪気払いの儀式として始まりました。
陰陽道と季節の変化: 節分は、陰陽道において季節の変化を祝う儀式として起源しています。陰陽道は陰と陽の対立や調和を考える日本の古い宗教的・哲学的な概念で、節分はその一環として、季節の変わり目を祝う重要な行事とされていました。
※諸説あり